
私は中学時代に心身の調子が悪くなってしまい、「武道」で身体を鍛えようと思い立ちました。
しかし、いきなり道場に行く勇気もなく、半年くらい自分で身体を鍛えていました。
その時にトレーニングの参考にしていたのが、「空手の理」という本です。

オガワの高校時代のバイブル

空手家の柳川先生が肉体的なハンデを負いながら、超人的な鍛錬を行う半生と独自の空手理論をまとめた本です。
空手をやらない人も読み物として面白いので、とてもおススメですよ。
今でもAmazonで販売されていますね。
私はこの本を元に高校時代は自分で鍛錬していました。
ですから、突き蹴りの練習も自分でアレコレしていました。
なもんで・・・
半年くらい自分で身体を鍛えて、体力的に自信がついてきた時に、本当は空手か少林寺拳法(もしくはテコンドー)をしたかったのです。
身体は柔らかかったので、実は「蹴技」をすごくやりたかったのです。
かっこいいですしね。


合気道には基本、蹴りがありません。
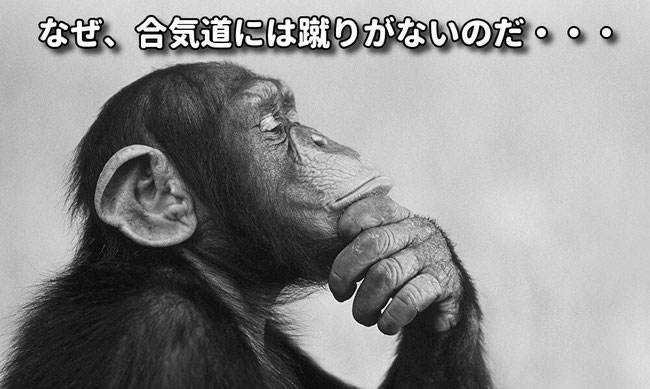
実は、合気道には「蹴り」がありません。
結局、一番通いやすかった(時間と場所)のと、TV番組(※)で塩田剛三先生の映像を見た事で、合気道を習う事に決めたのですが、やはり蹴りへの憧れはずっとありました。
しかし、合気道には蹴り技はないです。
これは植芝盛平開祖の
「人間は2本足で立っても不安定なのに、蹴りをして1本足になる事はない。」
というお考えからだそうです。
今は合気道はしっかり大地に立っている事が大切だと理解できるのですが、高校生の私は「蹴りがない事」に物足りなさを感じたものでした。
※たけし・さんま世紀末特別番組!! 世界超偉人伝説
佐々木先生が合気道に蹴りがない理由を説明した動画です。

とはいえ、植芝開祖は蹴りへも対応できた。
実は塩田剛三先生がはじめて植芝盛平開祖と立ち会った時、前蹴りを放ち、強烈に投げられたそうです。
塩田先生は柔道家だったので、虚をついて「前蹴り」を行ったそうです。
植芝盛平開祖は自らは蹴り技をしませんでしたが、蹴られた場合は完全に対応できたようです。
・18歳の頃、塩田の父親から相談を受けた府立六中校長の誘いで、植芝盛平が営む植芝道場を見学に訪問。その時期の塩田は武道の腕前を上げ慢心を見せ始めており、植芝と門下生の稽古も内心「インチキじゃないか」と思いながら眺めていたという。そこへ植芝自ら塩田に「そこの方、やりませんか」と声をかけ、1対1の稽古をしないかと誘ってきた。塩田はその申し出を受けて事実上の立ち会いに臨み、植芝へいきなり前蹴りを放った。すると一瞬で壁まで投げ飛ばされ、驚嘆した塩田は即日入門を決意。植芝の門下生となった。塩田は晩年に受けたインタビューの中で、この植芝との立ち会いのことを「投げられた時に頭をしたたかに打ちましてね。私より小さなお爺さんに何をされたのかも分からず、閉口してしまったわけです。その場で手をついて、弟子にして下さいと言いましたよ」と述懐している。これ以後、内弟子時代も含めて約8年間、植芝の下で修行に励んだ。
引用:wikipedia

蹴りを取り入れている流派もあります。

とはいえ、蹴り技の稽古を行っている合気道もあります。
合気道SAを代表とする試合を行う「フルコンタクト合気道」は蹴り技を行います。
つまり蹴り技への対応も習得できるという事です。
一般的な合気道では蹴り技は行いませんので、「蹴り技」に興味のある方はこれから紹介する合気道の流派がおススメです。
合気道SA
塩田剛三先生の内弟子だった櫻井文夫師範が平成3年に設立した、合気道の流派団体です。
積極的に組手や打撃を取り入れて研究されている流派です。
覇天会
藤嵜先生が合気道SAから独立し創設された流派です。
積極的に組手や打撃を取り入れて研究されている流派です。
ハプキドー
韓国の合気道と言われる「ハプキドー」です。
日本ではほとんど知られていません。
その歴史的背景には諸説あります。
そんな「ハプキドー」ですが、感じでは「合気道」と書きます。
技はかなりアクロバティックな印象です。
日本では習えないと思います。
戦前、日本で大東流合気柔術を学んだ崔龍述(チェ・ヨンス、Choi Yong Sul)が戦後、韓国で「大韓合気柔拳術道場」を開いたのが始まりとされる。
現在、韓国のハプキドーは複数の流派、団体が存在しており、ルールや練習法などが流派によって異なっている。
引用:wikipedia

海外では蹴り技の研究をされる先生も・・・

私は合気道の基本の習得をしっかり行っていきます。

蹴りの稽古をしていない合気道で、専門的に稽古されている方の蹴りを、軽くさばいて投げるという事は難しいかもしれません。
しかし、私なんかは蹴りへの対応どころか「合気道の基礎」もまだまだ納得できるレベルに稽古できていない状態です。
後、10年くらいは愚直に「合気道の基礎」を稽古していけたらなと思っています。
今は広げるより、深めていきたい気持ちが今は強いです。

蹴りを稽古しない合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館では、どなたでも2回まで無料で合気道体験をする事ができます。
合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから。
どなたでも2回まで無料で合気道体験をする事ができます。
あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、
下の画像をクリニックして、無料体験の内容を確認してみてくださいね(^^)
↓↓今すぐ、クリックして詳細をご確認ください↓↓

イチから分かる合気道のいろは
合気道未経験者向けに基本知識を分かりやすく、解説しています。
ぜひ、他の記事も読んでくださいね。
↓↓下の画像をクリックしてください。





コメントをお書きください