合心館京都・大阪の小川です。
合気道の稽古は投げて投げられての繰り返しです。
ですから、日々の稽古の半分は受身をとっていることとなります。
私たちがしている普段の合気道の稽古は「型稽古」です。
(とはいえ、合気道の型稽古は、他の武道の型稽古に比べて、ずいぶん自由度が高いですが)
乱取り稽古ではないので、受身も必要以上にがんばることなく受身をとります。
この辺りが他の武道や格闘技をされていた会員からすれば???に思うようです。

では合気道の型稽古で受身をとることの意義は何なのでしょうか?
私は以下の①~③の意義があると思います。
※重要度の優先順
①だけの意義であれば、頑張り合いも良いのですが、私たちは未熟な修行の段階です。
②③の意義のために、普段の稽古はすぐに転ばず、頑張り合いもせず、素直に受身取った方がメリットも多いのではと現段階では考えています。
(段の取得後、頑張る相手を倒す稽古も応用で研究してもいいかもしれません。)

①稽古で自分の身を守る

まずは何より優先することは、相手から技を掛けられた時に、怪我をしないように身体を守ることです。
これは他の武道も格闘技の受身も同じだと思います。
怪我をしては普段の生活に支障が出ますし、合気道もお休みしないといけません。
合気道は型稽古なので投げる方も、受身のレベルを観察して、相手のレベルよりほんの少しだけ上の負荷をかけてあげてもらえたらと思います(相手をよく観る)。
受けの方も、誰に投げられても自分の身を守れる受身を習得してもらえればと思います。
(バンバン飛受身ができないと、昇段できませんか?中高年の方から質問されますが、そんなことはありません。稽古で怪我をしないように受身をとれれば十分です。もちろん若い人はバンバン飛んでください。)
飛受身も怪我をしないために、飛んで回避するところから生まれてきたのだと思います。

②身体を柔らかく強く練る

二つ目の受身の意義として、身体を柔らかく強く練るというのがあると思います。
昔、何かの本で太極拳は「真綿のくるまった鉄」というのを読みましたが、合気道のそのような身体の状態になれたらなーというのがあります。
つまり、体軸や丹田などを練りたいのですが、それが固いものではなく、柔らかく練り上げたいと考えています。
なので、稽古では技を掛けるだけではなく、受身を取ることが大切なのではないでしょうか?
呼吸は吐いたら必ず吸います。
それと同じで、合気道の稽古も技を掛ける(吐く)と受ける(吸う)はワンセットが望ましいと考えます。
(指導者は多くの人を指導しないといけない場合は、受けてられないことも)


③先生や先輩の技を受けて盗む

私が合気道をはじめたころは、よく技は盗むものとよく言われていました。
今は懇切丁寧に指導を行う指導者が多いと思います。
それはとても良い事だと思います。
しかし、合気道には言葉では説明できない部分がたくさんあることも事実です。
最終的には技を盗む力といいますか、自分で取りに行く能力が必要になると思うのです。
技を盗むためには、先生や先輩の技を観ることと、技を受けることが大切ではないでしょうか?
なんかそんな気がします。
しらんけど・・・

■おすすめのブログ

こちらのブログも、ぜひ併せて読んでみてくださいね(^^)
分かってないのに、分かったようなこと書いています。

もし、あなたが合気道に興味をお持ちなら・・・

合心館京都・大阪では一人でも多くの方に合気道を知ってもらいたい!という思いから、無料体験を行っています。
合心館では誰でも「2回まで無料体験」をしていただけるようにしています。
2回まで体験をした後に、入会をするかどうかはご自身で判断していただけます。
あなたがもし、少しでも合気道に興味をお持ちなら、ぜひ合心館の無料体験にお越しくださいね。
↓↓今すぐ、クリックして「無料体験」の詳細をご確認ください↓↓
また、合気道の稽古で使用しない道場の空き時間をレンタルスタジオとして貸し出しもしております。
↓↓京都市内でレンタルスタジオをお探しなら、下の画像をクリックしてください。






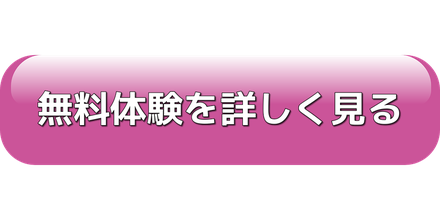

コメントをお書きください